この記事の目次
新潟高野連が決定した球数制限とは?
2018年12月22日、新潟県高等学校野球連盟(新潟高野連)が2019年春の県大会から、選手の体を第一に考える取り組みとして、投手の球数制限を導入することを決定しました。
< 新潟高野連が実施する球数制限内容 >
- 1投手が1試合で投げられる球数は100球まで
- 2019年春の県大会に実施
2018年春の選抜大会から導入されたタイブレークに続き、選手の故障予防措置として注目されています。
ちなみにこの決定は新潟高野連の独自規制であり、2019年2月までに追随する他の都道府県はありません。
日本高野連が新潟高野連の独自規制に”待った”をかける
2019年2月20日、日本高等学校野球連盟(日本高野連)は新潟高野連が決定した独自規制(球数制限)に関し、以下の理由から再考を申し入れることを決定しました。
- 勝敗に影響を及ぼす規則については、全国で足並みをそろえて検討していくべき
- 部員不足に苦慮する加盟校と多くの投手をそろえられる強豪校との差を助長する可能性がある
一方、日本高野連も選手の故障予防の必要性は理解しており、
新潟が一石を投じた。未来の高校野球発展には避けて通れない。重く受け取るべき。
と竹中雅彦事務局長が語り、2019年4月に『投手の傷害予防に関する有識者会議』を立ち上げることを発表しました。
新潟高野連の独自規制に”待った”をかけた日本高野連ですが、今後も検討事項として議論していく姿勢を見せるも、個人的はスピード感がなく、取りあえずファイティングポーズを見せただけに感じてしまいます。
著名人の意見
この件に関して、高校野球界だけでなくプロ野球やメジャーリーグなどから様々な声がきかれました。
斎藤佑樹(北海道日本ハムファイターズ)
議論されるのはいいこと。世の流れに左右されるのではなく、高野連がかじ取り期待している。
前田健太(ロサンゼルス・ドジャース)
高校生は自分で球数を制限できない。大人が制限を設けてあげることは大事なことだと思う。
ダルビッシュ有(シカゴ・カブス)
何でも挑戦した方が絶対にいい。新しいことを取り入れないと、球界自体も活性化していかない。
渡辺元智(横浜高校前監督)
球数制限を導入するのであれば、足並みをそろえるべきだし、科学的な裏付けも必要。今回の日本高野連の判断は、まさにその通りだと思う。
筒香嘉智(DeNAベイスターズ)
「球数制限をすれば、野球が面白くなくなる、待球作戦をする」などいろんな声が上がっているが、大事なのは子供達の将来。大人が中心になるのではなくて子供たちの将来を考えてあげることが一番優先。
私も筒香の意見に全面同意です。野球に限らずスポーツはルールの中でやるものですので、ルールが変われば変わったなりの面白さを感じるはずです。
さらに前田健太の『高校生は自分で球数を制限できない』も正論ですね。チームを背負ったエースが簡単にマウンドを降りるわけがありませんから。
私の意見は「球数制限に賛成」だが・・・
私の個人的な意見としては、球数制限に賛成です。もちろんこれだけでは十分ではありませんし、まだまだ改善の余地があるでしょう。
しかし、それでも何もやらないよりもマシですし、不十分なことがあれば改善すれば良いだけの話です。
球数制限に関して、必ずこのような反対意見が出てきます。
- 体格の異なる選手なのに、一様に100球で交代はおかしい(科学的根拠が無い)
- 多くの高校球児は、高校野球が競技としての野球を終える。その最後の舞台を取り上げるのか?
- 多くの投手をそろえられる強豪がさらに有利になる
体格の異なる選手なのに、一様に100球で交代はおかしい?
確かに言いたいことは分かります。しかし、こんなことを言っている限り前に進まないでしょ。
『一様に100球で交代』が嫌なら、何球ならいいのか?ってことになるだけ。結局、科学的根拠がないからどうのこうのという話になるわけです。
科学的根拠?医学的根拠?あるわけないでしょ!
投手にとって肩は消耗品ですが、同じ球数でも体の使い方で肩や肘のダメージは変わります。
強い相手に全力投球した150球と、弱い相手に楽々投げる150球。体力的にも精神的にも負担は全然異なります。
さらに違和感を感じた部位をかばうように投げた結果、別の部位に負担がかかって故障するケースもあります。
肩に少し違和感があったので、肘を下げて投げてみたら結構投げられるので続けていたら、逆に肘が痛くなってしまう場合。
一般人でも、膝を怪我してかばって歩いていたら、次の日に腰が痛くなることもあるのと同じですね。
こんなケースも含めて、正確な科学的・医学的根拠を見出せるわけが無いんです。
科学的・医学的根拠を待って次のステップに進もうとするのはナンセンスですし、当面変えなくて良いという意見としか思えません。
多くの高校球児は、高校野球が競技としての野球を終える?
まさに暴論ですね。
野球人生として考えると、その後も野球を続ける可能性の方が高いでしょ。野球経験者なら草野球をやる人だって多いはずです。
肩や肘を壊していなかったら、もっと草野球を楽しめたのに・・・というケースは意外と多い。
野球経験者として期待されて草野球チームに入って、肩が痛くて投げられない・遅いボールしか投げられないことで悔しい思いをしている人は沢山いる。
真剣な野球?競技としての野球?
草野球でも真剣に取り組めば、同じ野球でしょ。観客が多い少ないはあるかもしれませんが、草野球だからって真面目に考えて取り組む人が珍しいわけじゃない。
若くして肩や肘を壊すってことは、こういった未来を奪うことなんです!
多くの投手をそろえられる強豪がさらに有利になる?
これはその通りです。
ただでさえ、トーナメント方式では球数制限が無くても多くの投手をそろえられる強豪校の方が有利であり、それに拍車をかけることになるでしょう。
この点を解消するには球数制限だけでなく、さらに別の規定を設ける必要があると思います。
打者のファール制限も同時に採用すべき!
投手に球数制限を設けるなら、打者にもファール制限も採用すべきです!
これなら、高い能力があるエースが孤軍奮闘するチームでも、強豪校がカット打法や待球作戦に簡単に潰されにくくなります。
もちろん、完全に強豪校と普通校を平等にすることはできませんが。
ただ仮に球数制限だけが導入された場合、カット打法や待球作戦が常套手段になることは明らかですし、ますます勝利至上主義が蔓延する可能性があります。
それに対抗する規定は絶対に必要です。
日本高野連は迅速な対応を!
高校生では自分の判断で練習や投球を制限できません。これは自分の体を分かっていないというより、そういった圧力が精神的に追い込んでいるからです。
エースを任される投手が、そう簡単にマウンドを降りることを良しとしない風潮は昔からあります。
監督やコーチの期待に答えたい、チームメイトに迷惑をかけたくない・・・そんな思いがエースをマウンドに踏みとどらせてしまうのです。
このような問題はエースだけに限らず、投手なら誰でも抱えています。
そもそも、連投につぐ連投で孤軍奮闘していたエースが決勝戦で『肩が痛いので投げれません』は言いやすいものです。
しかし、一回戦・二回戦に打ち込まれた投手が三回戦を目の前に『肩が痛いので投げれません』って言い辛いですよね?
二番手・三番手の投手なら、少し肩が痛くても巡ってきた出番をフイにしたくないので、どうしても投げてしまうものです。
練習試合でせっかく巡ってきた登板機会に三番手投手が『肩が痛いので投げれません』って言ったら、もう二度と使ってもらえないと思うでしょう。
仮に監督がそんなことを言わなくても、コーチが選手に『お前、そんなこと言っていたら一生試合にでれないぞ!』と脅迫めいたことを言うこともあるでしょう。
本来は、選手が体の異変を感じたとき正直に言える環境があり、その選手の相談をしっかりと聞いてあげる・選手の意見を尊重してくれる指導者がいることが理想的だと思います。
しかし昔から高校野球にはそのような土壌はありません。
私は、選手に故障を誘発する球数を科学的・医学的に明らかにするより、そういった環境を作るほうが今の野球界には難易度が高いと思いますよ。
だからこそ、思い切った規定を制定する必要があるのではないでしょうか?

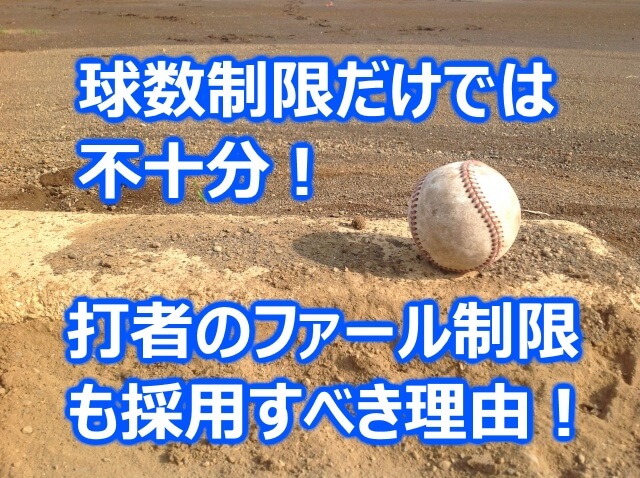










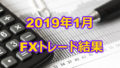
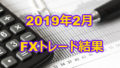
< 打者のファール制限 例 >
打者は2ストライク後に打てるファールは2球まで。それ以後のファールはアウトとなる。